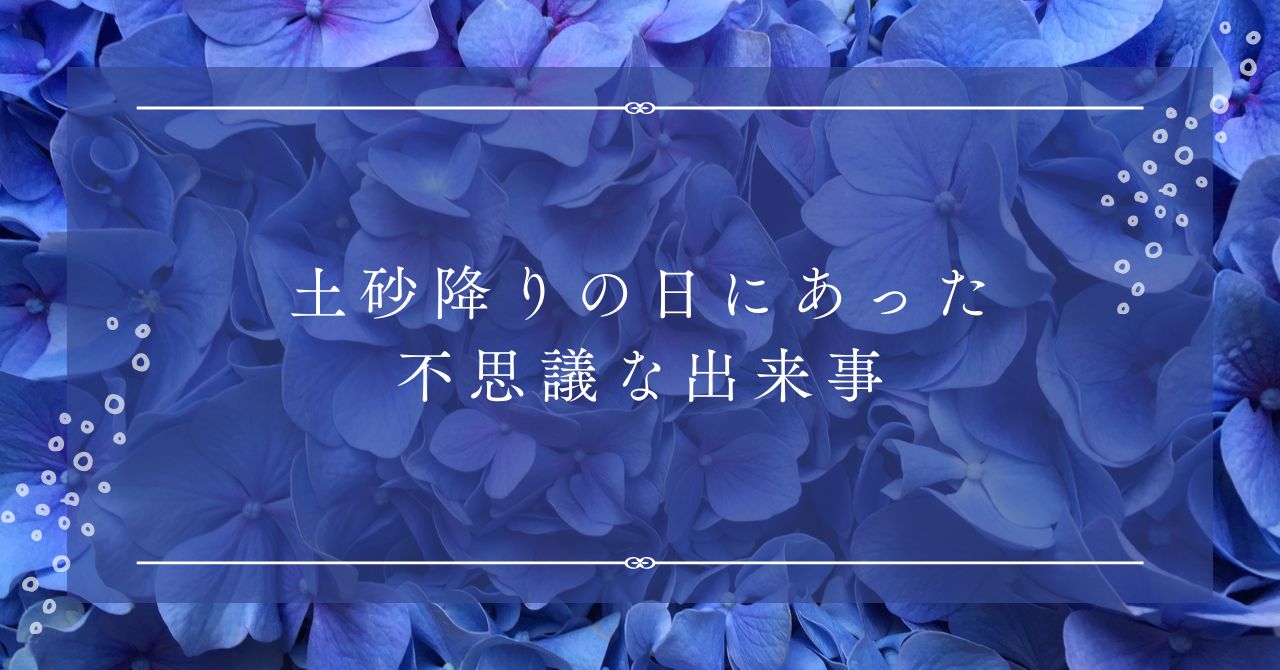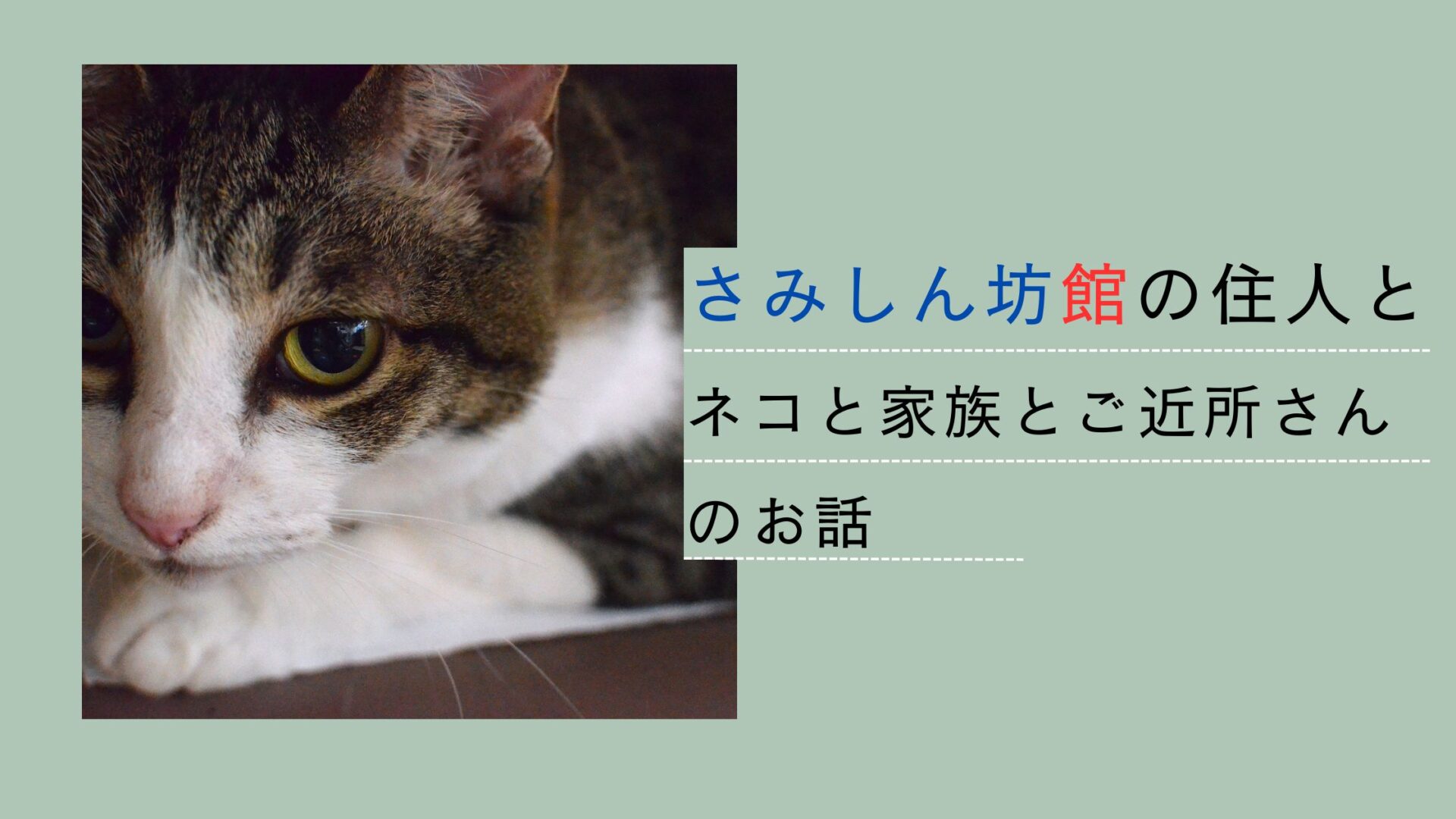未来の相談員の価値はなんだ?
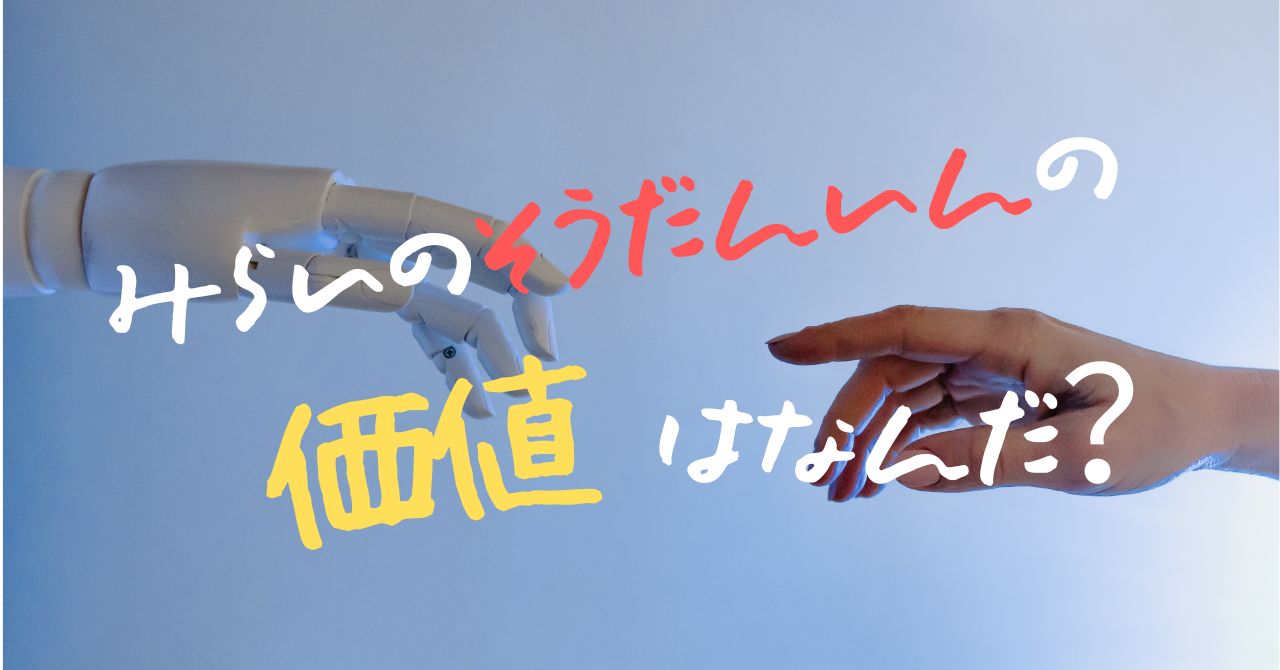
違和感を感じたアイスブレイク
先日、職能団体の交流会に参加した。
参加者は、現役の相談員ばかり。中には、相談員の社会福祉の専門書の筆者やメディアにご意見番として登場しているレジェンドも参加している。
緊張感の緩和させるために、運営側が提示したアイスブレイクがあった。
グループワークで「相談員の30年後はどうなっている?」というお題だ。
なんとまぁ~、センスがない!
おかみの考えは?
おかみの考えは、100年後も200年後も相談員の役割や価値は、大きくは変わらないと思う。
ただ、資格の名称や相談員の生計の立て方は、時代と共に変化はすると思う。基本的には社会福祉の力を必要とする人々はいつの時代も存在するのだ。
歴史を紐解いてみれば、相談を受けて解決に向けて動くことが職業化されたのが約100年前。国家資格化されたのが、約40年前だ。
それ以前は、相談員のような親切なご近所さんや相談員のような地域の有力者や相談員のような宗教家や相談員のような拝み屋さんが担っていた。今も、そのような人々を頼りにしている人はいる。
過去をさかのぼって考えてみても、相談員もしくは相談員のような人の役割や価値は変わってはいない。未来もきっとそうだ。
お~い あいつの存在を忘れてないかい?
いざ!グループワークを始めると、どのグループもAIの活用について話が盛り上がっている。
AIの力は否定はしない。
声帯や神経難病などでAIの技術を活用して、コミュケーションをしている人は、存在する。
発達障害や引きこもりの人が、AIだったらコミュケーションを楽しめるのではないか?なんて、アイデアが出た。
実際に、高齢者の分野ではAIでケアプランが作れないか?という議論がある。
それは、知ってる。
だけどね。
自分が、困ったときにAIに相談したいか?
ドラえもんぐらいの高いポテンシャルがあれば、相談してもイイかな?
30年後に、ドラえもんが存在するか?
答えは、NO!
30年後は、おかみは80歳。
そろそろ、福祉のお世話になる年齢だ。
その時は、相談事を人間に聞いてもらえない世の中になるのか?
冗談じゃないぞー!!
もやもやが止まらない
蓋を開けてみると、AIの力に期待する派閥が8割。AIの力を懐疑的に捉えている派閥が2割だった。
むしろ、AIに期待する派閥のほうが、「あんな事もできる、こんなこともできる」と、ランランと目を輝かせて発言している。
AIに懐疑的な派閥は、そもそもAIに対してドラえもんレベルの高いポテンシャルを求めているから、議論が噛み合わない。
それと、人間がAIに対して信頼や愛着が持てるか?と言う論点は、活用してみないと答えが出ない。そこをポジティブに捉えているかいないかの問題だ。
ドラえもんだって、のび太に対して間違った対応をしていることは多々ある。そこをリカバリーできる力があるから、ドラえもんはキャラクターとして愛されている。
ドラえもんが実用化し普及する未来があるとすれば、相談員も友達も無条件で愛してくれる親さえももいらなくなるだろう。
そうなると、生身の人間の価値ってなんだろう。
モヤモヤが、止まらない。
現時点では、ドラえもんはファンタジーだ
とにかく、ドラえもんは2112年生れの設定のキャラクターだ。
おかみが100歳まで生きるとして、死後さらに40年経過しないとドラえもんは生まれない。
おかみが、AIが発達した未来を確かめることは不可能だ。
そうなると、この議論をすることさえムダだ。
団塊の世代のレジェンドが、「私たちの世代は、反骨精神が強いからAIに相談しない。」という発言があった。
反骨精神?
何に対して?
ちょっと、その気持ちわかるけど(笑)
まぁ、レジェンドですから、AIに相談しなくても、自己解決できるし頼りになるご友人もたくさんいるだろう。
さすが、レジェンド。
あっぱれ。
そういう人、大好き。
現実の近未来は、どうなる。
ファンタジーはともかく。
AIが、アセスメントとスクリーニングと解決策の提案はできそうだ。
ただ、AIに正しく入力しないと、最適解は提案できない。
AIに情報を入力するのは、人間だ。
自身を取り巻く現実が直視できず、もしくはその能力が阻害されていることにより
、AIに正しく入力できないクライアントもいるだろう。
たとえ、頑張って現実を直視し最適な提案されても、実行するかどうか?は、別問題。
クライアントが、受け入れ難い提案だったとき、そっと誘うまたは背中をそっと押すのが相談員だ。
ほーら、相談員の価値は変わらない。
論破!!
自己満足!!